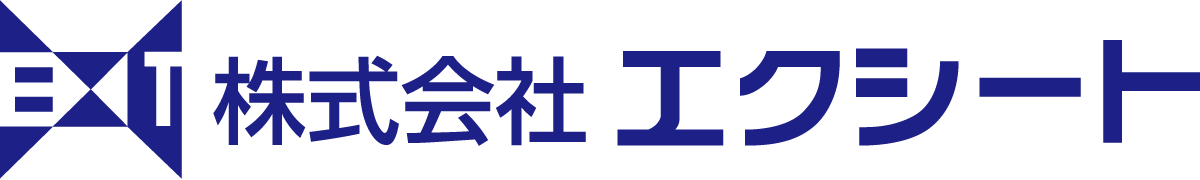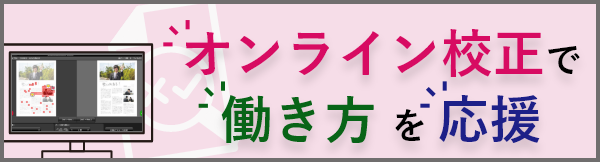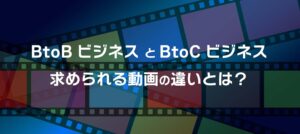印刷物の制作には校正作業がつきもの。
福井の印刷会社である当社でも、毎日のようにお客様との校正が繰り広げられています。
当たり前のように「校正」という言葉を使っていますが、どういう意味なのか調べてみると
校正(こうせい、英語: proofreading)は、印刷物等の字句や内容、体裁、色彩の誤りや不具合を、あらかじめ修正すること。
とありました。「不具合」と言われてしまうと、デザインしている側からすると、悲しくなりました…。
それでは、校正作業にはどんな手法が使われているか、元印刷営業(現企画・ディレクター)として福井県で活動してきた立場で考えてみました。
校正方法の種類
- 紙による校正
- メールによる校正
- オンライン校正システムによる校正
おおよそ3種類に分かれるかと思います。FAXを使う人もいるかもしれませんが、そちらは省略します。
それぞれのメリット・デメリットを考えてみましょう。
紙による校正
昔ながらの手法ですね。
印刷会社が自社のプリンタで出力した「校正紙」をお客様にお届けする手法です。
その場で打合せをすることもあれば、「置いてくるだけ」のパターンもあります。
私の感覚的には「置いてくるだけ」のパターンの方が多いのではないでしょうか?
印刷会社が自社のプリンタで出力した「校正紙」をお客様にお届けする手法です。
その場で打合せをすることもあれば、「置いてくるだけ」のパターンもあります。
私の感覚的には「置いてくるだけ」のパターンの方が多いのではないでしょうか?
紙による校正のメリット
- 営業マンと直接会って打ち合わせができるから、ニュアンスが伝わりやすい
- 色のイメージが確認しやすい
- お客様がプリントする手間がいらない
- 校正紙に直接書き込める
一番のメリットは、①だと 思います。
細かなニュアンスは直接会った方がニュアンスが伝えやすいイメージがありますね。
細かなニュアンスは直接会った方がニュアンスが伝えやすいイメージがありますね。
紙による校正のデメリット
- 営業マンが持ってこないといけないので、タイムラグが発生する
- 校正紙が1部だけのことも多いので、お客様が社内での共有がしにくい
いろんな人が書き込んで、校正紙が真っ赤かなことも… - 校正回数が多いと、どんどん校正紙が溜まってくる上、管理がしにくい
- 接触の機会となってしまうため、感染対策は必須
優秀な営業マンほど忙しいので、なかなか校正紙が届かないこともあったりします。
私が思うには、一番のデメリットは②だと思います。
複雑な案件な程、多くの人がかかわってくるため、社内共有をいかにうまくやるかが効率化のカギです。
私が思うには、一番のデメリットは②だと思います。
複雑な案件な程、多くの人がかかわってくるため、社内共有をいかにうまくやるかが効率化のカギです。
メールによる校正
現在、一番主流なのではないのでしょうか?
PDFで校正データを送ってもらい、直接メールに修正指示を記入するか、プリントして赤ペンをいれたものをスキャンして送るなどの手法が一般的です。
PDFで校正データを送ってもらい、直接メールに修正指示を記入するか、プリントして赤ペンをいれたものをスキャンして送るなどの手法が一般的です。
メールによる校正のメリット
- 営業マンの移動時間がない分、校正到着が早い
- メールのCCを使えば、簡単に社内共有ができる
- メールが受信できる環境であれば、どこでも確認ができる
インターネットの普及によって、各段に校正作業が楽になりました。
社内共有も手軽にできるのが利点です。
社内共有も手軽にできるのが利点です。
メールによる校正のデメリット
- 届いたPDFをプリントして、修正を書き込んで、それをスキャンして、メールに添付。意外と工数がかかる作業。
- 重いPDFデータだと受信できないため、ストレージサービスが利用が必要
特にスキャンしたデータは軽いと手書き文字が読めないことも。 - プリンタの違いで思っていた色と違うというトラブルが起こる可能性あり
- データ管理をしっかりしないと、最新のPDFがどれかが分からなくなることも
メールは普段から利用して言うツールのため、利用しやすいですが、
①のような面倒な手間が発生しているのも事実です。この作業をいかに効率化するかが、ポイントとなります。
もし、ペンタブなどPDFに直接書き込めるツールがあると、無駄なプリントアウトも必要なくなるのでおススメです。
私が行っていた校正PDFファイルの管理方法は下記のような感じです。ご参考まで。
- 校正PDFファイルのファイル名に番号をつける。最も大きい番号が最新の校正。
- フォルダを「進行中」「終了」「破棄前確認」と分けて、案件ごとにフォルダをつくり、状況に応じて各フォルダに格納。
- 「終了」フォルダはいつまで取っておくか自分でルール決めして、まずは「破棄前確認」に移動
- 月に1回、「破棄前確認」フォルダを確認し、必要ないものは削除。保管が必要な場合は、別フォルダで管理。
オンライン校正システムによる校正
コロナ流行により、多くの印刷会社が導入を始めていますが、
chromeやEdgeなどのブラウザを利用して、校正確認や修正指示が書き込めるツールです。
オンライン校正のメリット
- インターネット回線があれば、いつでもどこでも校正確認が可能
- 修正がされた場所を2画面で確認できる
- ブラウザ上で直接指示を記入することができ、いちいちプリントする必要がない
- 校正を一元管理することができ、ユーザーを追加すれば、社内共有も楽ちん。
- 過去の校正もデータとして残っているため、すぐに確認できる
- 入稿データもドラック&ドロップで可能
校正作業の効率化を検討されているのであれば、現在では最も効率化できる手法といえます。
オンライン校正のデメリット
- 極端にPCのスキルが低い人だと使いこなせない可能性あり
- プリンタの違いで思っていた色と違うというトラブルが起こる可能性あり
オンライン校正の一番のデメリットは「使えるか」どうかです。もっと言えば「使おうとしてくれるか」どうか。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が推進されている中であっても、「現状が最適」という考えの方も少なくありません。
オンライン校正システムもいろいろありますが、Wordが多少触れる人であれば、問題なく使えると思います。
「現状が最適」と考える人にいかに使ってもらえるかが、一番のデメリットといえるでしょう。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が推進されている中であっても、「現状が最適」という考えの方も少なくありません。
オンライン校正システムもいろいろありますが、Wordが多少触れる人であれば、問題なく使えると思います。
「現状が最適」と考える人にいかに使ってもらえるかが、一番のデメリットといえるでしょう。
福井の印刷会社であるエクシートは「オンライン校正」を推進しています
弊社では福井県でいち早く数年前から「オンライン校正」を導入しています。
多くのお客様がその便利さを実感していただき、「もう離れられない」という広報担当者様もいるぐらいです。
弊社に印刷物をご発注いただける方であれば、無料でご利用いただけますので、詳しくは下記のバナーをクリックしてみてください。
※オンライン校正システムを販売しているわけではございません。
たまにお問い合わせがあるので…。
たまにお問い合わせがあるので…。